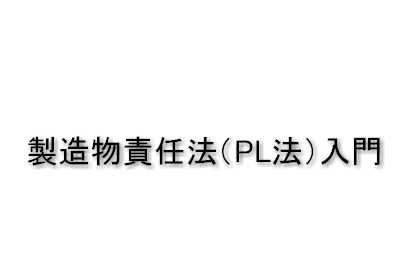
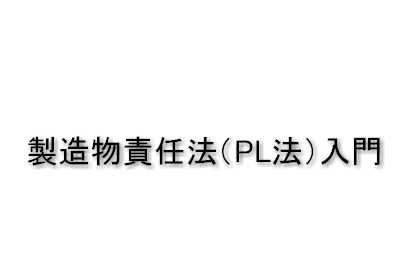
(C) copyright Hisamichi Okamura, 1999, All rights reserved.
第1章 総 論
1.製造物責任の意味(第3条)
最初に、この法律の内容を簡単に紹介する。
一般に、製造物は、メーカーから卸売業者を経て小売店に卸され、それがエンドユーザーである消費者に販売されることになるが、この法律の内容は、例えば製造物に欠陥がありエンド・ユーザーが損害を被った場合、エンドユーザーが小売店などを飛び越えて、直接、メーカーに対し無過失責任を負わせ、損害賠償責任を追求できるというものである。
責任を追求できる者としては、エンド・ユーザーだけでなく、損害を受ければ第三者でも責任を追及できる。
以上のような意味が、この法律の第3条に記載されている。
2.制度趣旨(第1条)
PL法が制定された趣旨は、第1条に「目的」として記載されているが、分かり易く説明すると、次のようなものであるといわれている。
すなわち、「欠陥」として良く挙げられる例としては、買ったテレビが火を噴いたり爆発したりして人が大怪我をしたり死亡したようなケースである。
この場合、このテレビを販売した小売店には民法570条の規定する売主瑕疵担保責任に基づき一定の範囲で責任が認められることになるが、法律的な責任の範囲はせいぜいテレビの代金程度にとどまり、代金を返してもらっても人命や健康に関する救済にはならない。
販売業者に過失があれば契約責任を追求して広い範囲の損害を賠償してもらえることになるが、小売店は、自分で設計したり製造したりしているわけではないので、欠陥についての過失責任が認められるケースは稀である。
また、仮に小売店に何らかの過失責任が認められる場合でも、零細な小売業者の場合には、支払能力が乏しい場合も多い。
他方、欠陥品を製造したメーカー自身に責任を負わせようとしても、メーカーとエンド・ユーザーとの間には、直接の契約関係は存在しないので、従来は民法709条以下に定められた不法行為責任により責任を追及するほかなかった。これを「過失責任の原則」というが、この規定では、訴えた消費者の側が過失を立証しなければならないので、責任追及は、なかなか困難である。
客観的に見て欠陥があっても、メーカーに予見可能性や回避可能性がなければメーカーに過失有りとすることはできないからであり、消費者は、メーカーの工場内を覗くわけにもゆかず、専門技術的なことについて素人である消費者が検討を加えることも難しいからである。
そこで、このような困難さを避けるためにメーカーに無過失責任を負わせたのが、PL法が作られた理由であるということになる。
3.保護される被害者の範囲
したがって、本来は消費者保護がPL法の主たる目的であるが、欠陥品により被害を受けた者であれば、例えば企業のように、いわゆる末端消費者個人以外であっても保護されると規定されている。
例えば、企業が他のメーカーから購入した素材その他の半製品に欠陥があった場合は、当該企業がメーカに責任を追及できるわけである。であるから、企業としては、自社がメーカーとしてどのような責任を負わされるのかという観点から検討するだけでなく、自社が被害者になった場合に、PL法を使って、どのような責任追及をすることができるかという観点からも検討しておく必要があり、その意味で、両面から検討する必要があることになる。
4.民法上の責任との関係(第6条)
もっとも、この法律ができたということで、従来の民法上の責任がなくなったということにはならない。この法律の第6条には「製造物の欠陥による製造業者等の損害賠償の責任については、PL法の規定によるほか、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による。」と規定されている。
つまり、消費者の側からすると、メーカーの責任を追求する極めて強力な道具がひとつ増えたことになる。
第2章 対象とされる物(第2条第1項)
1.対象
それでは、我が国のPL法で、どのような物が製造物責任の対象となるかといえば、PL法の第2条第1項で、対象となる「製造物」とは、「製造又は加工された動産」をいうものとされている。
ここに「製造」とは、部品又は原材料に手を加えて新たな物品を作り出すことであり、「加工」とは、物品に手を加えてその本質を保持しつつこれに新しい属性又は価値を付加することをいうものとされている。
したがって、例えば未加工の農産物などは、部品や原材料に手を加えて製造されたわけでもなく加工されたわけでもないので、製造物責任の対象とはならない。
これに対し、農産物を加工して漬物にした際に、有害物質が混入したようなケースでは、漬物は製造物責任の対象となる。
また「加工」はPL法の対象となるが、「修理」は対象とならない。
両者の区別は時として困難であるが、取りあえずは、「加工」は何かを付け加えるものであるのに対し、「修理」は元に戻すことという意味として区別するほかない。
2.不動産
次に、PL法は、動産を対象としたものであるから、目に見えないサービス自体や、目に見える物でも、動産と違って不動産には原則として適用がない。
造成した宅地も、上物(うわもの)である建物自体も動産ではない。
したがって、不動産である宅地造成や建築物の工事に欠陥があっても、原則として、PL法による責任が発生するわけではない。
これは、建売住宅ではなく単にビルなどの請負をして請負工事に欠陥があった場合でも同様である。不動産については、施主との関係では民法上の契約責任でまかなわれるにとどまる。
また、建物の不具合により第三者に被害が生じた場合には、民法に戻って、土地工作物責任(民法717条)による救済がなされることになる。製造物責任以外のこれらの法律上の責任については、後から詳しい説明を加えるが、なぜ、立法のプロセスで、不動産についてPL法の適用が除外されたかというと、前述のような民法による救済手段が用意されているだけでなく、建物は耐用年数が長く、その間の劣化や維持・補修を十分に考慮する必要があること、EC諸国でも不動産は製造物責任の対象外なので、国際的な制度との調和が必要であることなどが理由とされている。
もっとも、何が不動産なのか動産なのかについては、その範囲は必ずしも明らかでない。PL法には、何が動産であるのか不動産であるのかについて定義した規定は置かれていないからである。
そこで、一般原則に従い、民法の規定を手がかりにすることになる。
この点については、民法86条という規定があり、この規定によると、不動産とは、有体物の中で、土地及びその定着物をいうものとされている。
定着物というのは、建物や樹木の他、石垣やテレビ放送用の鉄塔など、付着された土地に吸収され土地とは別個独立とされないものとされている。
他方で、経済的に独立の価値があり、簡単に移動できる仮小屋、足場、公衆電話、仮植中の樹木は定着物でないので不動産ではなく動産である。
したがって、これらの仮小屋などに欠陥があった場合にPL法の対象になることは争いがない。
もっとも、仮植中であっても樹木は「製造又は加工された」という物ではないので、この点で、PL法の対象とはされないであろう。
3.ソフトウェア・プログラム
ソフトウェア単体の場合は、おおむねこの法律は適用されず、したがってまた、ソフトウェアベンダーは製造物責任を負わないと考えられている。
その理由であるが、この法律にいう「製造物」とは、「製造又は加工された動産」をいうと規定されていまる(
2条1項)。したがって、コンピュータ・ソフトウェア単体は、動産ではないので製造物責任の対象とならないというのが立法時の政府見解であり、学説でも異論なく認められている考え方である。
ちなみに、これに対し、機械に組み込まれた場合には動産であるから対象になるとされている(通商産業省産業政策局消費経済課編「製造物責任法の解説」(通商産業調査会、
1994年)67頁、経済企画庁国民生活局消費者行政第一課編「逐条解説・製造物責任法」(商事法務研究会、1994年)59頁)。したがって、埋め込みマイクロチップは製造物責任の対象となりうる。
問題は、ソフトウェア単体と埋め込みマイクロチップとの中間形態である。
このような中間にあたるのが、まず、OSやソフトウェアがプレインストールされたコンピュータである。これについては、ソフトウェアに欠陥があった場合、ハードウェアとソフトウェアのメーカーが同一であれば製造物責任法の対象になるが、ハードウェアとソフトウェアのメーカーが同一でなければ、ソフトウェアに欠陥があっても製造物責任法の対象にならないと考える説、プレインストールされることによって製造物の一部になったとする説(岡本佳世ほか「企業のPL対策」(商事法務研究会、1995年)67頁)など、説が対立している。
次に、
CD-ROMやFDなどの物理的な外部記憶媒体に記録されて納品されたり販売されているソフトウェアも、製造物責任法の対象となるのかどうか問題となりそうに思われる。しかし、一般的には、やはり製造物責任法の対象とならないと考えられている。
その理由として、「ハードの場合にはソフトと一体となって機能を発揮するうえで、それ自体も不可欠の作用を果たし、人の目にはむしろソフトも含めた全体がハードの機能として意識されるのと異なり、FD等の媒体自体はそのような機能をもたず、単にソフトを入れて運ぶための容器のようなものであるから、この解釈は無理だろう。」(速水幹由「PL法適用業種・非適用業種の責任と法務戦略(3))」NBL(商事法務研究会)595号37頁)という点が指摘されている。
第3章 責任主体-誰が責任を負わされるか(第2条第3項)
1.第1号
次に、建設会社は自社で部材を製造していないので安心かというと、そうでもない。
PL法の第2条第3項を見ていただきたい。ここに、誰が製造物責任を負わされるのかということが定義されている。
第1号は、「当該製造物を業として製造、加工又は輸入した者」と記載されている。
ここで注意が必要なのは、「製造、加工」だけではなく「輸入した者」も責任を負わされるということである。
つまり、自分で外国から部材を輸入すれば、自分で製造や加工をしていない会社であっても、PL法が適用されるリスクを負うことになることを意味している。
これは、被害者が海外の製造業者に直接責任を問うことは困難であるから、とりあえず輸入業者に責任を負わせ、後日、輸入業者が海外の製造業者に求償してゆけばよいという考えに基づいている。
そうすると、大手の建設会社が、円高の恩恵を考えて、自社で大量輸入した部材を使って建築しようという新規プロジェクトを企画した場合に、当該部材に欠陥があって被害が発生したときは、これを輸入したことに基づき、PL法に基づく賠償義務を負わされることになる。
2.第2号
さらに、第2号は「自ら当該製造物の製造業者として当該製造物にその氏名、商号、商標その他の表示(以下「氏名等の表示」という。)をした者又は当該製造物にその製造業者と誤認させるような氏名等の表示をした者」にも責任を負わせることを規定している。
これは「表示製造業者」と呼ばれており、この意味は少し分かり難い。
まず、第2号前段の「自ら当該製造物の製造業者として当該製造物にその氏名、商号、商標その他の表示をした者」というのは、要するに、主としてOEM製品の供給先がこれにあたるものとされている。
OEM製品の供給先は、ほとんどの場合、自社で設計や製造をしているわけではないが、製造者としての外観を製品に付与した以上は、これに対する消費者の信頼を保護すべきとの考え方からPL法の責任主体とされているのである。
次に、第2項後段の「当該製造物にその製造業者と誤認させるような氏名等の表示をした者」というのは、主としてプライベート・ブランドの販売業者を指している。
そうすると、OEM製品やプライベート・ブランド商品に欠陥があったときは、製造元は1項で、供給先は第2項で、連帯して責任を負うことになる。
3.第3号
ついでに、第3号の「前号に掲げる者のほか、当該製造物の製造、加工、輸入又は販売に係る形態その他の事情からみて、当該製造物にその実質的な製造業者と認めることができる氏名等の表示をした者」に関しても説明をしておく。
これは、例えば、製品によっては、製造元の名前を一切出さずに、発売元が自社名で広告をしているようなケースがあり、特に薬品などにはよくみられる。
このようなケースでは、往々にして製造元は中小企業であって、発売元は大企業であることが多い。
このような場合、消費者は有名な大企業の製造して製品であると誤解して購入することがあり、こういったケースで発売元に責任を負わせるという趣旨である。
このような第3号の場合はともかく、第2号のOEM製品やプライベート・ブランドで部材の供給を受けて建築した場合は、やはり、いくら製造していなくともPL法で責任を負わされることになるという事実は、覚えておいていただく必要があると思われる。
この場合、一旦損害賠償に応じておいて、その後に実際に製造したメーカーに対して求償をしなければならないことになる。
4.リース業者、レンタル業者、販売業者などの供給者
以上の立場の者が、PL法により責任を負わされることになるのに対し、リース業者、レンタル業者、販売業者などの供給者は原則として責任を負わない。
これらの者は、いくら欠陥製品の最終提供者であるとはいえ、自社で設計や製造に関与したわけではないので、製造物の技術内容の詳細を知ることができる立場にはないからである。
ここで原則として責任を負わないと言ったのは、これらの者でも第1号の輸入業者に該当したり、第2号や第3号に該当する場合には、例外的に責任を負わされることになるからである。また、ここで責任を負わないと言ったのも、PL法により責任を負わされることがないという意味にとどまり、PL法以外の民法による責任を負わされることはあり得るので、一切責任を負わないという意味ではない。
第4章 「欠陥」とは
1.「欠陥」の意味(第2条第2項)
PL法は「欠陥」についての責任である。いくら無過失責任といっても、何ら欠陥がなければ責任を負うことはない。
そこで、何がPL法に言う「欠陥」に該当するかという点が問題となる。
PL法にいう「欠陥」とは、第2条第2項に定義されており、「当該製造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいう」とされている。
欠陥には、次の3つの種類があるといわれている。
① 設計上の欠陥
製造物の設計段階で十分に安全性に配慮しなかったために、製造される製造物全体が安全性に欠ける結果となった場合。
② 製造上の欠陥
製造物の製造過程で粗悪な材料が混入したり、製造物の組立に誤りがあった等の原因により、製造物が設計・仕様どおりに作られず安全面を欠く場合。
③ 指示・警告上の欠陥
有用性ないし効用との関係で除去し得ない危険性が存在する製造物について、その危険性の発現による事故を消費者側で防止・回避するに適切な情報を製造者が与えなかった場合。
2.欠陥の判断に際し考慮すべき事情
どのような事情を考慮して「通常有すべき安全性を欠いている」と判断するのかについては、この点は条文自体に、「当該製造物の特性、その通常予見される使用形態、その製造業者等が当該製造物を引き渡した時期その他の当該製造物に係る事情」を考慮すると記載されている。
まず、「当該製造物の特性」という点については、次のように説明されている。
例えば、包丁は鋭利な刃物であるから、その意味で使い方次第では危険なものである。
しかし、切れない包丁では使い物にならない。
鋭利な刃物でなければ意味がないのである。
したがって、もし、包丁で指を切った人が、その包丁が鋭利であるから危険であって欠陥があると主張したとしても、刃物である包丁が鋭利で危険だからというだけで欠陥があるということにはならないことは当然である。
このような意味で、「当該製造物の特性」という点を理解願いたい。
次に、「その通常予見される使用形態」というのは、例えば、マンションの室内で花火をした人がいて、その結果として畳に火が燃え移り火事になったとする。
この場合、畳に火が燃え移るほどの火が出る花火だから欠陥があるということはできないであろう。
問題は、通常の人であれば室内の畳の上で花火をするようなことはないし、してはいけないことは判っているはずであるという点である。
そういう意味で、合理的に予見できる通常人の使用形態ということが問題となるということである。先ほどの包丁の例では、包丁は料理に使用するものであって、戦争ごっこの武器として使用するものではない。
世の中は広いので、そのような非常識な人がいることは全く予見できないわけではないが、通常人の使用形態という見地からは合理的に予見できるわけではないのである。
他方で、いくら取扱説明書で用途を限定してあり、当該用途外の使用方法がなされた場合であっても、それが通常人の使用形態という見地からは合理的に予見できる使用方法であれば、PL法の対象となる。
なお、「その製造業者が当該製造物を引き渡した時期」というのは、後述する。
さらに、「その他の当該製造物に係る事情」としては、その例として行政上の安全基準があげられている。
しかし、行政上の安全基準というのは、守るべき最低基準を定めた取締法規であって、これを守ったからといって、必ずしも責任がないということにはならない。
もっとも、行政上の安全基準をクリアしておれば、守るべき最低基準を満たしていることになり、実際には欠陥がないとされる可能性が事実上は高い。
3.免責事由(第4条)
A.免責ということの意味
もっとも、欠陥があれば、常にメーカー等は責任を負わされるというものでもない。
PL法の第4条は、メーカー側の「免責事由」を定めている。
「免責」という法律用語は、本来は原則として責任を負わされるのだけれども、例外的に一定の事情が存在することを立証した場合には、責任を免れるという意味である。
PL法の第4条が定める「免責事由」には、第1号の「開発危険の抗弁」といわれるものと、第2号による免責事由がある。
どちらか一方が立証されれば、メーカー側は責任を免れることができるが、どちらについても、メーカー側に立証責任がある。
ここに立証責任があるというのは、メーカー側で、これらに該当すべき事実の裏付け証拠を出さなければならないと言うことであり、そうである以上、もし、裏付け証拠が不十分なため、これらに該当すべき事実が本当に存在しているかどうかにつき裁判官がどちらともいえないと思った場合は、メーカー側が裁判に負けてしまうということを意味している。
B.第1号
そこで、まず第1号の「開発危険の抗弁」であるが、法律を見ると、「当該製造物をその製造業者等が引き渡した時における科学又は技術に関する知見によっては、当該製造物にその欠陥があることを認識することができなかったこと」と書かれている。
要するに、製造物の引き渡し時点の科学技術の水準では欠陥があるかどうか判りようがなかった場合には、メーカー側は責任を免れるという意味である。
例えば、昔は「チクロ」という人工甘味料があり、厚生省でも認められていたので、「みつ豆」の缶詰などには普通に使われていた。
ところが、ある時、発ガン性があることが判り、以後は、これを使ってはならないということになった。
昔の段階では、誰も、「チクロ」が発ガン性がある有害物質であるかどうかを知ることは不可能であったから、もし、昔、PL法が存在していて「チクロ」は有害物質だといって訴えた人があったとしても、この「開発危険の抗弁」により、「チクロ」製造メーカーは責任を負わずに済んだことになる。
C.第2号
次に、第2号は「当該製造物が他の製造物の部品又は原材料として使用された場合において、その欠陥が専ら当該他の製造物の製造業者が行った設計に関する指示に従ったことにより生じ、かつ、その欠陥が生じたことにつき過失がないこと。」を免責事由としている。
この意味も、一度読んだだけでは分かり難いので、具体例で説明する。
例えば、ある自動車メーカーのような完成品メーカーが下請業者を使って部品を作らせた場合に、部品の仕様や規格などはすべて完成品メーカーが定め、下請業者は機械と手間だけを提供するというような場合がある。
ところが、指示された仕様や規格どおりに製造したところ、完成品メーカーが定めた仕様や規格自体の誤りにより部品に欠陥が生じるという事態が発生することがある。
こういう場合にまで下請業者に製造物責任を負わせるのは余りに過酷であるので、下請業者の責任を免れさせたのが本号である。
もっとも、下請業者が責任を免れるためには、完成品メーカーの指示に従うと欠陥が発生することを知ることができなかったというように、下請業者に過失がなかったことも必要とされている。
これが、「かつ、その欠陥が生じたことにつき過失がないこと。」の意味するところである。
第5章 PL法に基づく「責任」の内容
1.PL法に基づく「責任」とは
PL法に基づく責任とは、第3条に規定されているとおり、欠陥により他人の生命、身体又は財産を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償するという責任である。
先に述べたような、買ったテレビに欠陥があって火を噴いた事例で、これにより人が大怪我をしたり死亡したという人身損害だけでなく、火を噴いた結果、家が火事で燃えてしまったというような物件損害についても負わされることになる。
もっとも、火事が発生したことを苦にして住民が自殺したような場合についてまで責任を負わなければならないかどうかは別である。
裁判所の考え方によれば、過失責任については、欠陥と相当因果関係のある損害の限度で賠償すれば良く、およそどんな損害でも賠償しなければならないわけではないものと考えられており、PL法についても、同様の考え方が当てはまるものと言われている。
次に、PL法では、これに続いて、但書で、「その損害が当該製造物についてのみ生じたときは、この限りでない。」としている。
つまり、欠陥のため燃えてしまったテレビ自体についてはPL法による責任を負わない。
これは、大元の原因がテレビの欠陥であるから、一見すると奇妙に感じられる。しかし、テレビ本体程度については販売店の責任を追及すれば足りるから、敢えてPL法によるまでもないとされたのである。
問題は、先程の事例のように、テレビが消失しただけでなく、同時に、人が怪我をしたり家が燃えたりした場合にも、この但書が適用されるかどうかという点である。
もし適用されるとすると、人が怪我をしたり家が燃えたりした損害についてはメーカーに損害賠償請求し、テレビ本体の損害については販売店に請求することになり、分けて裁判をしなければならないことになって不便この上ない。
そこで、このように、テレビ本体以外にも損害が発生した場合は、但書は適用されず、まとめてメーカーに責任を追及できるものと考えられている。
2 PL法に基づく責任追及期間の制限(第5条)
第5条で、「被害者又はその法定代理人が損害及び賠償義務者を知った時から3年間行わないときは、時効によって消滅する。その製造業者等が当該製造物を引き渡した時から10年を経過したときも、同様とする。」とされているが、このうち10年という期間は、「身体に蓄積した場合に人の健康を害することとなる物質による損害又は一定の潜伏期間が経過した後に症状が現れる損害については、その損害が生じた時から起算する。」とされている。
そうすると、やはり、いつ引き渡したか、出荷したかを記録にとどめておく必要があることになる。
ところで、製品に添付された保証書で、保証期間を1年と定めておくように、PL法に基づく以上の責任追求期間を例えば1年に限定することができるかどうかが問題となるが、このようなことは許されず、これを定めても無効となる。
なお、契約責任の時効期間は10年である。
したがって、損害及び賠償義務者を知った時から3年間経過したときは、製造物責任は問えなくとも契約責任は問えることになる。
また、不法行為責任は、製造物責任と同様に、損害及び賠償義務者を知った時から3年間で時効消滅するが、そうでない限り、事故が20年以内に起これば不法行為責任は追求することができる点で、10年以内とされる製造物責任よりも重い。
つまり11年目に事故が発生したときは、製造物責任は問えないけれども不法行為責任は問えるのである。
3 免責特約
当事者間で免責特約や責任制限特約が締結される場合がある。
かかる免責特約等は、もともと特約の当事者以外の第三者を拘束するものではない。
なお、製造者等が、取扱説明書や製品の表示などで免責特約を記載していることがあり、その場合、このような記載がエンドユーザーを拘束するかどうかという点が問題となるが、立法時における衆議院の商工委員会での1994年6月10日の説明では、エンドユーザーを拘束するものでないという説明がなされている。
それでは、免責特約等の当事者間における効力については、どのように考えるべきか。
この点、民法の不法行為の原則によるが、公序良俗違反(民法90条)として無効と解される場合が多いと考えられている(経済企画庁国民生活局消費者行政第一課編「逐条解説・製造物責任法」(商事法務研究会、1994年)128頁)。
第6章 補足 - PL法関連のウェブサイト
経済企画庁「製造物責任(PL)法について」
http://www.epa.go.jp/pl/pl-j.html
住宅部品PLセンター (財)ベターリビング
http://www.iijnet.or.jp/PLC/index.html
住宅関連紛争事例集
.財団法人 自動車製造物責任相談センター
http://www02.so-net.ne.jp/~aadr/
富山県中央会「製造物責任法(PL法)」
http://www.chuokai-toyama.or.jp/report/pl1.htm
香川県中央生活センター「PL法クイズ」
http://www.pref.kagawa.jp/chuoseikatsu/menu08/quiz41.htm
日野法律特許事務所「コンピュータ・プログラムとPL法」
http://hino.moon.ne.jp/prov10.htm
PL法を活かし、情報公開法を求める関西連絡会
http://www.c-net.co.jp/PL.html
以 上